

- 専門は,視覚情報処理,視覚心理学,心理データ解析などです.
- 視覚情報処理に関しては,運動視における情報処理,光沢感,まぶしさ感などの研究をしてきました.心理物理学的実験や情報処理モデリングなどにより,ヒトの視覚について研究しています.
- 色における印象や絵画知覚などといった視覚心理学についての研究も行っています.
- その他に,機械学習や信号処理の手法を使った,心理学におけるデータ解析について研究しています.ヒトの性格の分析,オノマトペによる知覚空間の推定などといったことを行っています.
- 研究テーマ:
- 運動視: 視覚システムが,どのように運動情報を処理しているのかについて調べています.
- 視覚的運動情報の空間的相互作用:周りのものが動いているとそのものが動いていなくても動いてみえることがあります.そのような運動情報が空間的相互作用がどのようにして生じるのかについて研究しています.
- 自己進行方向知覚: 視覚システムが,どのように運動情報を使って動いている方向を計算するのかを調べています.
-
- 傾いた絵画の知覚.: 私たちは普通,傾いた絵画を見ても歪みに気づきません.どうして歪みが知覚されないのかについて検討しています.
- まぶしさ感:ある種のグラデーション画像は,輝いて見えます.そういった画像はグレア刺激などとも呼ばれます.グレア刺激によるまぶしさ感について研究しています.
- 光沢感:色が光沢感に与える影響などについて調べました.
- 視覚心理学:色に関する印象などについて調べています.
- 心理データ解析:信号処理の手法である独立成分分析(ICA)などを心理データに適用する方法について研究しています.
- SD法データの独立成分分析による解析:色の印象についてSD(semantic differential)法で調べ,データを独立成分分析による分析を行いました.
- オノマトペ:オノマトペにより,材質感の知覚空間について検討しました.
- 性格:ヒトの性格を独立成分分析などを使って分析しています.
視覚的運動情報の空間的相互作用
- 周辺のものが動くと中心にあるものが反対方向に動いて見えることを運動対比,同じ方向に動いて見えることを運動同化といいます.ノイズの大きさが大きくなると,運動知覚が運動対比から運動同化に変化する傾向があることを報告しました.
- 見えやすいと運動対比,見えにくくなると運動同化が生じやすくなるという仮説を,見えやすさをノイズとコントラストを変化させることで検討しました結果は,ノイズが高いときは運動同化が生じやすくなるが,コントラストが低い時は運動対比が生じやすいことを明らかにし,上記の仮説が成り立たないことを示した.
- コントラストが高いとき,刺激が大きくなると,運動方向の判断がしにくくなることが報告されているが,刺激が急に提示されることが重要な要因と示唆されていた.反応時間を使って,その効果を検討したところ,刺激が大きくなることによる運動方向判断の成績低下は,刺激が急に提示されたときに生じ,静止刺激があらかじめ提示されてから動き出したときには生じないことを報告しました.
- 研究論文
- Hanada, M. (2012). Investigation of center-surround interaction in motion
with reaction time for direction discrimination. Vision Research, 59, 34-44.
- Hanada, M. (2010). Differential effect of luminance contrast reduction and noise on motion induction. Perception, 39(11), 1452-1465.
- Hanada, M. (2004). Effects of the noise level on induced motion. Vision Research, 44 (15), 1757-1763
自己進行方向知覚の研究
- 環境中を移動しているとき,どこに向かっているのかを知ることができます.また,実際に動かないでも,視覚刺激だけで自己運動の知覚は生じます.例えば,ドライビングシミュレーターやフライトシミュレーターによる視覚刺激で,自分が動いているように感じます.
視覚運動情報により,自己が進んでいる方向(自己進行方向)がどのように知覚されるのかについて研究してきました.心理物理実験によって,視覚的運動情報による自己進行方向知覚の特性について調べました.運動による自己進行方向知覚のモデリングを行いました.
- 研究論文
- Hanada, M. (2005). Computational analyses for illusory transformations
in the optic flow field and heading perception in the presence of moving
objects. Vision Research, 45 (6), 749-758.
- Hanada, M. (2005). An algorithmic model of heading perception. Biological Cybernetics, 92 (1), 8-20.
- Hanada, M., & Ejima, Y. (2000). Heading judgement from second-order
motion. Vision Research, 40 (24), 3319-3331.
- Hanada, M., & Ejima, Y. (2000). Method for recovery of heading from
motion. Journal of the Optical Society of America A, 17 (6), 966-973.
- Hanada, M., & Ejima, Y. (2000). Effects of roll and pitch components in retinal flow on heading judgement. Vision Research, 40 (14), 1827-1838.
- Hanada, M., & Ejima, Y. (2000). A model of human heading judgement in forward motion. Vision Research, 40 (2), 243-263.
まぶしさ感の研究
- 中心が一様な色で,周辺部分がグラデーションのある画像を見ると,発光していたり,輝いたりして見えます.コンピュータグラフィックスではそういった画像を,グレアと呼びます.(照明の研究では,グレアという語を違う意味で使います.)
 研究で使用したとグレア刺激
研究で使用したとグレア刺激
- グレア刺激の周辺部のグラデーションの輝度プロフィールの違いによって,まぶしさ感が変化することを報告しました.
- 周辺部の色が,青っぽいか,赤っぽいときの方が,黄色や緑,無彩のとき色より,まぶしさ感が強くなることを報告しました,中心部の色の効果は小さいものの,中心部と周辺部の色が違うときの方が,同じときより,まぶしく感じることも示しました.
- 研究論文
- Hanada, M. (2019). Effects of peripheral gradient of color saturation on the feeling of being dazzled. Perception, 48(5), 412-427.
- Hanada, M. (2015). Effects of colors on the feeling of being dazzled evoked by stimuli with luminance gradients. Perceptual and Motor Skills, 121(1), 219-232.
- Hanada, M. (2012). Luminance profiles of luminance gradients affect the feeling of dazzling. Perception, 41(7), 791-802.
光沢感の研究
- ハイライトの色(鏡面反射成分の色)が物体の色(拡散反射成分の色)と異なると,光沢感が強くなることを報告しました.ハイライトの色と物体の色が不自然な組み合わせでも光沢感が強くなることも示しました.
- 研究論文
- Hanada, M. (2012). Difference between highlight and object colors enhances
glossiness. Perceptual and Motor Skills, 114(3), 735-747.
傾いた絵画の知覚
- 込んだ美術館では正面から絵画を鑑賞することができず,斜めから見なければならないときがあります.斜め方向から絵をみると,正面から見たときとは違った像が目に投影されます.しかし,私たちは斜めから鑑賞してもそれほど違和感を持つことはないと思います.斜めから見た絵画がどのように知覚され,どのような視覚処理が行われているのかについて検討しました.
- 研究論文
- Hanada, M. (2005). Phenomenal regression to the frontal and natural picture.
Vision Research, 45 (22), 2895-2909.
色彩調和の研究
- 色彩調和した 配色を見たときと,不調和な配色を見たときで,脳波が異なるのか調べました.視覚誘発電位を比較したところ,P300 と呼ばれる成分が,色彩調和・不調和で異なることを報告しました.
- 学会発表
- 花田光彦 (2012). 色彩調和・不調和判断の事象関連電位 日本心理学会第76回大会.
色と感情の対応関係の研究
- 赤は怒りや興奮,黄色は幸福,緑は冷静さなど,色によって感情が想起されたり,対応づけられたりします.色と感情の連想関係について,どのような関係があるのかについて,対応分析という手法を使って分析しました.色相環をラッセルの感情の円環モデルに対応づけることで,色と感情の連想関係が生じるのかを検討しましたが,そうではないことを示しました.
色と感情は,温度,もしくは,活動度に媒介されて対応づけられているようであるということを示しました.
- 研究論文
- Hanada, M. (2018). Correspondence analysis of color -emotion associations.
Color Research & Application, 43(2), 224-237.
色と形の対応関係の研究
- 丸には赤,尖った不規則な形は黄色といったように,特定の形には,相応しいと感じる色があります.その対応関係を調べ,感情は,あまり形と色の対応関係を媒介しておらず,知識による連想やや慣習的な対応づけの役割が大きいのではないかという結果を報告したました.
- 研究論文
- Hanada, M. (2019). Associations of visual forms with colors: The minor role of emotion as the mediator. Color Research & Application, 44(4), 568-580.
独立成分分析による心理学データの分析
- SD(semantic differential)法のデータは主に因子分析を使って分析されてきました.色の配色の印象をSD法で測定し,そのデータに対して,独立成分分析を適用しました.負の尖度を持つ独立成分分析を行うと,解釈可能な分析結果が得られることを示しました.
- 研究論文
- Hanada, M. (2013). Analyses of color emotion for color pairs with independent
component analysis and factor analysis. Color Research and Application,
38(4), 297-308.
オノマトペによる知覚空間の研究
- オノマトペを使用して,視覚的な材質感知覚における知覚空間の構造を調べました.視覚的判断をしても,触覚の知覚空間に使い構造が得られることを報告しました.材質感の判断には,触覚的なものが優先されることが示唆されます.
- 研究論文
- Hanada, M. (2016). Using Japanese onomatopoeias to explore perceptual dimensions
in visual material perception. Perception, 45(5), 568-587.
性格の分析
- ヒトの性格について,独立成分分析などを使って分析しています.
- 学会発表
- 花田光彦 (2015). 記述形式による性格構造の分析 −有名人の性格に関する質問紙を用いて− 日本心理学会第79回大会.
- 花田光彦 (2014). 独立成分分析による性格構造の分析 日本心理学会第78回大会..
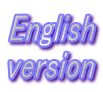



 研究で使用したとグレア刺激
研究で使用したとグレア刺激