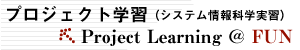| Q1a |
グループのなかでの自分の役割: |
|
     |
|
64 |
 |
責任と権限が明らかであった (26%) |
|
133 |
 |
責任と権限がある程度決まっていた (54%) |
|
34 |
 |
責任と権限はあまり決まっていなかった (14%) |
|
7 |
 |
責任と権限はほとんど決まっていなかった (2%) |
|
4 |
 |
その他(1%)
|
| Q2a |
自分の所属するプロジェクトの難易度: |
|
     |
|
39 |
 |
非常に難しかった (16%) |
|
154 |
 |
難しかった (63%) |
|
36 |
 |
比較的易しかった (14%) |
|
2 |
 |
非常に易しかった (0%) |
|
11 |
 |
その他 (4%)
|
| Q3a |
プロジェクト学習で習得した方法(複数回答可): |
|
             |
|
189 |
 |
プロジェクトの進め方 (9%) |
|
213 |
 |
複数のメンバーで行う共同作業 (11%) |
|
173 |
 |
発表(含むポスターの作成)方法 (9%) |
|
188 |
 |
報告書作成方法 (9%) |
|
193 |
 |
学生同士でのコミュニケーション (10%) |
|
132 |
 |
教員とのコミュニケーション (6%) |
|
161 |
 |
技術・知識の習得方法 (8%) |
|
124 |
 |
技術・知識の応用方法 (6%) |
|
96 |
 |
作業を楽しく行う方法 (5%) |
|
108 |
 |
作業を効率よく行う方法 (5%) |
|
157 |
 |
課題の設定方法 (8%) |
|
167 |
 |
課題の解決方法 (8%) |
|
15 |
 |
その他 (0%)
|
| Q4a |
プロジェクト学習で習得したかったが、習得できなかった方法(複数回答可): |
|
             |
|
25 |
 |
プロジェクトの進め方 (5%) |
|
10 |
 |
複数のメンバーで行う共同作業 (2%) |
|
19 |
 |
発表(含むポスターの作成)方法 (3%) |
|
9 |
 |
報告書作成方法 (1%) |
|
20 |
 |
学生同士でのコミュニケーション (4%) |
|
43 |
 |
教員とのコミュニケーション (8%) |
|
36 |
 |
技術・知識の習得方法 (7%) |
|
83 |
 |
技術・知識の応用方法 (16%) |
|
69 |
 |
作業を楽しく行う方法 (13%) |
|
93 |
 |
作業を効率よく行う方法 (18%) |
|
30 |
 |
課題の設定方法 (6%) |
|
26 |
 |
課題の解決方法 (5%) |
|
30 |
 |
その他 (6%)
|
| Q5a |
プロジェクト学習と今までに受けた講義・演習との関連の有無: |
|
     |
|
126 |
 |
3つ以上の講義・演習と関連があった (52%) |
|
62 |
 |
2つの講義・演習と関連があった (25%) |
|
31 |
 |
1つの講義・演習と関連があった (12%) |
|
18 |
 |
講義・演習とまったく関連がなかった (7%) |
|
5 |
 |
その他 (2%)
|
| Q6a |
プロジェクト内での教員同士の連携: |
|
     |
|
42 |
 |
非常に良い (17%) |
|
135 |
 |
良い (55%) |
|
27 |
 |
悪い (11%) |
|
13 |
 |
非常に悪い (5%) |
|
25 |
 |
その他 (10%)
|
| Q7a |
グループ内での作業分量の割当: |
|
     |
|
14 |
 |
公平に割り当てられていた (5%) |
|
99 |
 |
ほぼ公平に割り当てられていた (40%) |
|
99 |
 |
多少不公平があった (40%) |
|
21 |
 |
非常に不公平があった (8%) |
|
9 |
 |
その他 (3%)
|
| Q8a |
通常の活動時の教員の指導の有無: |
|
     |
|
68 |
 |
適切に指導してくれた (28%) |
|
93 |
 |
おおよその指導はしてくれた (38%) |
|
43 |
 |
指導はあったが不十分であった (17%) |
|
28 |
 |
ほとんど指導をしてくれなかった (11%) |
|
8 |
 |
その他 (3%)
|
| Q9a |
最終報告書・ポスター作成に関する教員の指導の有無: |
|
     |
|
65 |
 |
適切に指導してくれた (27%) |
|
120 |
 |
おおよその指導はしてくれた (50%) |
|
36 |
 |
指導はあったが不十分であった (15%) |
|
12 |
 |
まったく指導をしてくれなかった (5%) |
|
7 |
 |
その他 (2%)
|
| Q10a |
通常の講義・演習と比較して、プロジェクト学習の意義の有無※プロジェクト学習をやめて、通常の講義・演習にした方が良いかどうかに関する質問です。: |
|
     |
|
157 |
 |
プロジェクト学習の意義があった (65%) |
|
59 |
 |
どちらかといえばプロジェクト学習の意義があった (24%) |
|
12 |
 |
どちらかといえば通常の講義・演習の方が意義がある (5%) |
|
3 |
 |
講義形式の方が意義がある (1%) |
|
9 |
 |
その他 (3%)
|
| Q10c |
その理由として考えられる項目を選択してください。(複数回答可): |
|
          |
|
144 |
 |
グループ内での自分の役割 (18%) |
|
97 |
 |
自分の所属するプロジェクトの難易度 (12%) |
|
149 |
 |
プロジェクト学習で習得した方法 (19%) |
|
33 |
 |
プロジェクト学習で習得したかったが、習得できなかった方法 (4%) |
|
78 |
 |
プロジェクト学習と今までに受けた講義・演習との関連の有無 (9%) |
|
45 |
 |
プロジェクト内での教員同士の連携 (5%) |
|
95 |
 |
グループ内での作業分量の割当 (12%) |
|
67 |
 |
通常の活動時の教員の指導の有無 (8%) |
|
48 |
 |
最終報告書・ポスター作成に関する教員の指導の有無 (6%) |
|
26 |
 |
その他 (3%)
|
| Q11a |
自分の所属するプロジェクト(グループ)の活動に対する満足度: |
|
     |
|
55 |
 |
非常に満足 (22%) |
|
113 |
 |
満足 (47%) |
|
57 |
 |
やや不満 (23%) |
|
12 |
 |
非常に不満 (5%) |
|
3 |
 |
その他 (1%)
|
| Q11c |
その理由として考えられる項目を選択してください。(複数回答可): |
|
          |
|
130 |
 |
グループ内での自分の役割 (16%) |
|
114 |
 |
自分の所属するプロジェクトの難易度 (14%) |
|
138 |
 |
プロジェクト学習で習得した方法 (17%) |
|
57 |
 |
プロジェクト学習で習得したかったが、習得できなかった方法 (7%) |
|
65 |
 |
プロジェクト学習と今までに受けた講義・演習との関連の有無 (8%) |
|
47 |
 |
プロジェクト内での教員同士の連携 (6%) |
|
95 |
 |
グループ内での作業分量の割当 (12%) |
|
66 |
 |
通常の活動時の教員の指導の有無 (8%) |
|
43 |
 |
最終報告書・ポスター作成に関する教員の指導の有無 (5%) |
|
26 |
 |
その他 (3%)
|
| Q12a |
1週間あたりのグループ単位の作業時間: |
|
     |
|
84 |
 |
6コマ以上 (35%) |
|
100 |
 |
4コマ以上6コマ未満 (41%) |
|
47 |
 |
2コマ以上4コマ未満 (19%) |
|
5 |
 |
2コマ未満 (2%) |
|
3 |
 |
その他 (1%)
|
| Q13a |
1週間あたりの個人単位の作業時間(グループ単位の作業時間を除く): |
|
     |
|
106 |
 |
6コマ以上 (44%) |
|
59 |
 |
4コマ以上6コマ未満 (24%) |
|
49 |
 |
2コマ以上4コマ未満 (20%) |
|
14 |
 |
2コマ未満 (5%) |
|
11 |
 |
その他 (4%)
|