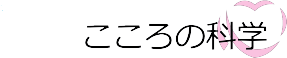脳と食品
このページでは、ストレス症状にあわせた解決メカニズムをHSPの観点から提示します。
そもそもストレスって何?
[1]ストレスがもとになって発症する病気は数多くあり、胃潰瘍、うつ病、PTSD、不眠症のほか、ガンやアルツハイマー病や心筋梗塞などあげればきりがないほどあります。つまり、ストレスとは体を病気にするものであると位置づけすることができます。
ストレス応答って何?
[1]ストレスとは体を病気にするものと位置付けられていると述べました。しかし実際、私たちの体はストレスを感じるたびに病気になっているでしょうか?なっていませんよね。このようにストレスによって病気になることを防いでいるのがストレス応答です。つまり、ストレス応答が十分に働かなくなった時に病気になるといえます。

ここまで読んだみなさんはきっとこう思ってるはずです
ストレス応答がストレスを受けたときに十分に働くようにする方法はないの!?
もちろんあります!!
ストレス応答はアダプティブサイトプロテクションによって強化することができます。
弱いストレスが強いストレスに強くさせる?
人間はストレスがないといきていけない
[1]ある程度のストレスは人間にとって必要です。なぜならば、弱いストレスを与え続けると生物は強いストレスが襲ってきたときにも対処できるようになるからです。このことをアダプティブサイトプロテクションと呼びます。学校に入学したてのころは緊張や不安でおなかがいたくなったりするが時間が経つと学校にもなれはじめておなかがいたくなくなるといった経験がある人も多いと思いますがこれもアダプティブサイトプロテクションです。
アダプティブサイトプロテクションが起こるメカニズムって何?
[1]その前にまずはなぜストレスを受けると病気になるのかを知りましょう。人間の体が70%の水分で構成されていることは知っている人が多いと思います。しかし、実は水分に次いでタンパク質が20%を占めています。
ストレスを受けると体内のたんぱく質が変性します。変性とはストレスによってタンパク質の立体構造がおかしくなることです。変性が起こりタンパク質の立体構造がおかしくなると、もともともっているタンパク質の働きが行えなくなり病気になります。
タンパク質がタンパク質の働きを助ける!?
先ほどアダプティブサイトプロテクションは弱いストレスを与え続けると強いストレスにも打ち勝てれるようになることだと述べました。ではなぜ弱いストレスを与え続けると強いストレスにも打ち勝てるようになるのでしょうか?
それにはHSP(ヒートショックプロテイン)と呼ばれるタンパク質のタンパク質の変性を防ぐ働きと変性したタンパク質をもとに戻す働きが関係しています。このHSPがストレスを受けたときに発生することがわかっています。つまり、弱いストレスを与え続けていると体内のHSPの量が増え続けるため、強いストレスを受けても増えたHSPが細胞を守ってくれるため強いストレスに打ち勝つことができるというわけです。
HSPはどうやって増やすの?
[1]HSPはヒートショックプロテインといわれるように熱ストレスによって発生しやすいものです。なので、サウナに入ったり、少し熱い42度ぐらいのお風呂に15分程度はいるなど体に熱ストレスを与えることによって増やすことができます。この程度なら忙しい大学生のみなさんも簡単に実践できるのではないでしょうか?また、食事においては温野菜など体が温まる食事をとることによって増やすことができます。

文責 小笠原建弘
参考文献
[1]水島 徹(2012) HSPと分子シャペロン 講談社
[2]石浦章一(2014) タンパク質はすごい! 技術評論社
[3]村上郁也(2010) イラストレクチャー認知神経科学: 心理学と脳科学が解くこころの仕組み オーム社