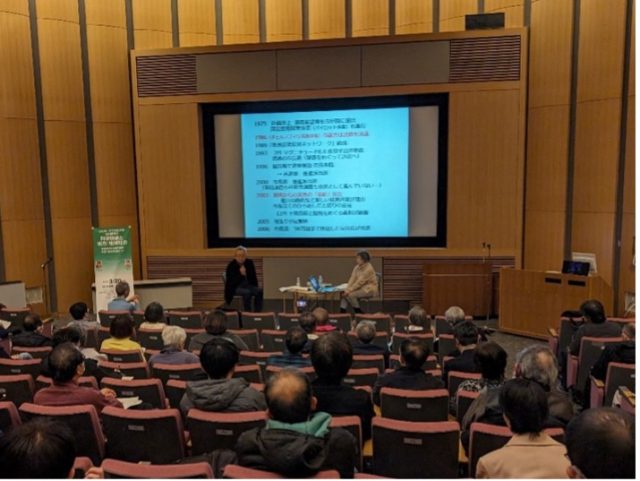[Message for FUN]
雑誌編集や研究広報などの仕事を経て大学教員になったという、幅広い経歴をお持ちの田柳恵美子先生。前任者から引き継いだ技術者倫理の授業では、進化するAIなど時代に即応したカリキュラムを試行錯誤してきたそうです。インタビューでは、先生ご自身の研究をふまえた地域連携の在り方、これからの時代を生きる上で大切な「センスメイキング」という社会への姿勢についても語っていただきました。

AIとの出会いから20年
広報・出版から研究コミュニケーションへ
私は20代のとき、広報や出版の仕事をしていました。ちょうどそのころ第2次AIブームというのが起こり、哲学や心理学と情報技術が学際的に融合する新分野に強い興味を抱いて、当時の上司にAIの雑誌をやりたいと言ったところ、『AIジャーナル』という雑誌を創刊することになり、1985年から2年間、編集を担当しました。当時まだ若手で、日本のAI研究を牽引していた中島秀之さん(のちに未来大学長、現札幌市立大学長)をインタビューしたり、まだ大学院生だった松原仁さん(のちに未来大教授、東大教授、現京都橘大教授)などを取材したり、一緒に座談会をやったりしました。その後、AIブームが沈静化して10年以上、ほとんど交流はなかったのですが、あとから振り返ってみれば、このときの出会いが、未来大で働くことになるそもそもの発端でした。
その後、フリーランスになり企画編集の仕事を続けていましたが、科学技術分野の仕事の依頼が多かったこともあり、次第に研究機関や自治体の研究広報・研究評価を専門的にコンサルティングするようになりました。2000年代には、地域経済振興を産学官連携で進めようという気運が高まり、文部科学省の知的クラスター事業、経済産業省の産業クラスター事業といった、大学との連携を柱とする政策が登場して、私も当時通っていた大学院の立地する石川県から依頼されて、研究評価報告書や研究計画を作る仕事をしていました。
こうしうたキャリアが評価されて、国の大学政策や産学官連携関連の委員なども多数経験し、専門的な知見をたくさん得ることができたのは、社会人大学院での研究にも大いに生かされました。

国の研究機関での実践を博士論文に
さて、『AIジャーナル』は残念ながら2年で廃刊となり、中島さんや松原さんとその後も制作に携わった『AI事典』という大著を1988年に発刊したのを最後に、その後しばらくAI研究者との交流は閉ざされていました。その間、私は先述のようにフリーランス編集者として、科学技術系を中心に様々な仕事をしていました。
そうこうしているうちに15年が経って、2003年にうれしいニュースが届きました。『AI事典』の改訂第2版が共立出版から出版されることになり、その打ち上げに呼ばれて、久しぶりに関係者の方々とお会いして旧交を温めることができたのです。そして私の近況を知った中島さんから、当時センター長を務めていた産業技術総合研究所(産総研)サイバーアシスト研究センターの研究広報を手伝ってほしいと頼まれました。
広報といっても、研究員が何をやっているかを見て理解して、それを社会連携などにつなげていくというような仕事です。ちょうど産総研では、2005年に名古屋で開催される「愛・地球博」という万博に向けて、他の研究機関や大学、民間企業等との産学官連携で、政府館の展示や、会場のアート作品の展示を、情報技術で支援するための研究開発、現場で使う端末装置などの実装開発に取り組んでいました。こうした活動をつぶさに観察・取材し、広く広報するための冊子を作ったりしました。
また当時は、大学や研究機関に対して、研究を市民へ積極的にコミュニケーションしていく「科学コミュニケーション」が求められ始めた時代でもありました。産総研でも、情報技術を社会へ市民へと発信していくために、さまざまなゲストを招いたシンポジウムを開いたり、小人数で肩の凝らないトークを行うサイエンスカフェを開いたりもしました。
そうした仕事ぶりを見て、大学院の指導教員から「社会人が論文を書くなら、仕事と関連づけるのが強みになる」とアドバイスされ、博士論文のテーマは、産総研での一連の研究コミュニケーションの観察と実践を題材にしました。国の研究機関に所属する研究員たちが、研究室から社会に出て、実社会や市民と積極的に繋がる活動そのものに、博士論文の題材となる貴重な発見がたくさんあったのです。

49歳で大学教員となり、未来大へ
技術者倫理という専門教養
2008年に博士号を取得すると同時に、未来大で教員として働き始めました。49歳でした。当初の3年間は特任教員として東京サテライトに勤務しながら、学生の就職活動の支援や、首都圏の同窓生と大学を繋ぐ活動、大学の10周年記念誌の編纂などの社会連携業務を担当しつつ、引き続き自分自身の研究を進めるために海外調査へ出たりしていました。
1年目が終わる頃に、ちょうど「技術者倫理」の授業を担当していた先生が定年退職されるということで、「田柳さんが適任だ。引き継いでくれないか」と声をかけていただきました。授業を隔週にしてもらって、東京から函館に通いながら担当することになりました。
技術者倫理は全員必修の専門教養科目で、学年全員250名(当初は4年次、現在は3年次)を相手にする大教室講義です。工科系専攻の国際基準として技術者倫理科目は必須とされていたので、教科書も多数出回り始めていた時期でした。何冊か手に取ってみて、技術者倫理というテーマがいかに広範にわたるかを察知しました。技術者倫理教育に関する海外の論文をいくつか見てみると、やはりテーマが広範でオムニバス形式であることから、学生からすると「技術者倫理とは何か」の一貫性をつかみにくいという問題点が指摘されていました。そこを自分なりに工夫して、学生の立場からの学習目標を分かりやすくすることや、激しく変化する情報技術の状況をキャッチアップしてカリキュラムを絶えず改変するよう努めてきました。ゼロからの取り組みの部分も多く自分にとって勉強であり、また研究テーマとして科学研究費補助金もいただきました。
正解がない問題を体感してもらう
技術者倫理の教科書やeラーニングの教材には、正解が用意されている演習問題が掲載されたりしています。それは善悪が明確な問題だから正解があるのですが、現実的に社会に出て技術の仕事をする人は、日々善悪の不明瞭なさまざまなことに立ち向かって判断しないといけないわけです。例えば、クライアントに納期を無理強いされた時にどうするかとか、予算がなくて相手の希望をすべて入れられないときにどう納得してもらうかとか、日々の仕事の中に倫理的態度が必要な場面がたくさんあります。
技術者倫理の授業では、そういう正解がない複雑な問題に、倫理的態度をもって対処していく力を身につけてもらいたいと思いました。正解は試行錯誤の中で見つける。自分たち1人1人の内面性、モラルと、外から要請されるエシックスを調和させて、グレーゾーンの中でそれぞれの譲れない一線を築き上げていこうと、シラバスの授業目標ではっきり謳いました。
250人規模の大講義ですが、授業では毎回、1人1人正解が違ってくるような課題を出して、2択3択の究極の選択をした上で、その理由を400字程度の短いエッセイで書いてもらいました。例えば、「データ隠蔽を告発した同僚が自宅謹慎させられた場合、あなたはその同僚をどのように支援しますか?」といった質問を出して、「表に出て異議申し立てをする/背後から支援する/自分も謹慎になったら嫌だから何もしない」から態度を選んでもらう。そして次の回で、全員の回答とエッセイを共有します。そうすると、正義感が強く「そんな会社にはいられない」という人から、「自分はきっと家族が大事だから黙って見ている」という人まで、バラエティーに富んだ答えがあることをつかんでもらいます。
技術者倫理として重要な点は、知識をうまく活用して論理構築し、上司や会社に大きな観点から働きかけて説得しようとする態度です。例えば、「そんなことは長くは続かない」「隠蔽はいつか絶対に世の中から批判される」「社員のやる気を失わせているだけだ」といった意見を、世の動きや過去の事例などに照らしながら批判的かつ建設的な意見を提示する。そういう倫理的態度を構築しようとする学生の回答例を全員に見てもらい、学生同士の相互学習を図ることが最も大切です。
世の中、全員が一丸となって道徳的正義に向かうわけではなく、腰が引ける弱気な人から前のめりになる強気な人、冷静に事態を俯瞰できる人までさまざまな人がいて、そうした多様性の総和で技術者倫理が生まれるのです。周りと自分の意見の違いが理解できると、技術者倫理とは何か、技術者倫理を実践するとはどういうことかが、少しずつ体感されてきます。
複雑化する技術にどう向き合うか
授業では、歴史的に有名な衝撃的な事件も取り上げました。アメリカのチャレンジャー号爆発事件(1986年)は、毎年「もう昔話だし、そろそろ止めようかな」と迷うのですが、打ち上げ数十秒後に宇宙飛行士を乗せたスペースシャトルが木っ端微塵に爆発する映像は、学生にものすごい訴求力があるようで、結局最後まで取り上げ続けました。この事件ではシャトル打ち上げ前日になって、外部委託企業の技術者から「この予想外の低気温状態で発射させたら危ない」と異議申し立てがあったものの、経営陣にNASAを説得させることができず、結局は技術者の予言通りの事故が起きてしまいました。打ち上げ場所のマイアミが、極寒の異常気象に襲われていわゆる「想定外」の事態を招いたのですが、技術者にも読みの甘いところがありました。学生たちには「こんなことが起こり得るんだ」ということを強く印象づける事例でした。
一方でここ数年は、AIやIoTといった先端的な情報技術が凄まじい勢いで進展し社会に広がり、情報系技術者の倫理観が問われる局面が増えてきたので、新しい話題を増やしてきました。例えば、AI兵器を戦争に使うことについての論争や、自動運転の事故責任は誰が取るべきなのかといった問題ですね。他にもビッグデータ分析を警察の捜査や人材採用などで使うと、過去の犯罪歴、成績や業績、嗜好・性向、民族や出身地などの偏ったバイアスをそのまま学習してしまうので、特定の出自を持った個人が不当に差別を受けてしまいやすいという問題があります。AIに社会的な正義や公正さを学習させられるかというと、それもまた難しくもあり危険でもあります。最近は生成系AIをめぐる倫理的問題も議論されていますが、私よりもむしろハードに使いこなしている学生の方が断然詳しいので、そうした猛者の意見を取り上げて紹介したりもしました。
ここ2、3年、こういった社会情勢の渦中にある未来大の学生に対して、「あなたはAIの開発者も社会的倫理や法的問題について見識や知識を持つべきだと思いますか?」という質問をするようになりました。「持つべきだ」という肯定の答えが多くなることは予想していたのですが、その一方で「いや、技術者は技術に専念すべきだ」という人も2〜3割は必ずいて、どちらの意見にも一理あるのです。こういうことを学生のうちに議論しておくことで、社会に出てからの自分の立ち位置について、深く考える機会になればと思います。

もう1つの使命、社会連携
地域と大学の距離感
科学技術広報や研究コミュニケーションの一方で、地域イノベーション研究というのも、もう1つの私の専門領域です。2000年代にはイタリア、ドイツ、フランス、スペイン、北欧などヨーロッパの先進地域に調査に通って、当時盛んだった産学官連携政策や知財・技術移転政策の研究に没頭していました。こうした専門性も評価されて、未来大では共同研究センターという、大学と外部を繋ぐ役割を担う部署に専任教員として所属しました。2000年代に入って全国各大学にはこうした「共同研究センター」という組織が設置されたのですが、直観的にそろそろより広く社会と大学を繋ぐ名称に変える時期が来ると思い、私から大学へ提案して、2013年に「社会連携センター」へ名称変更しました。
研究という面では、地域と大学はいまだ距離があります。大学の科学技術をそのまま地域の企業が活用したり、地場産業に応用できるかというと、かなり難しいのです。1990〜2000年代は、世界中で地域産業政策の中心に産学官連携を掲げていましたが、2000年代に入るとヨーロッパでも産学官連携の恩恵がなかなか地域経済に落ちていかない問題が浮上していました。私自身、いくつかの工科大学でそういう声を直接聞きました。
ミラノ工科大学では、1990年代には地域産業との共同研究コンソーシアムが華やかで、潤沢な研究資金を得ることができていたのですが、EU統合によって中堅企業の多国籍化・グローバル化が一挙に進み、力のある企業が以前のようにミラノに固執しなくなり、コンソーシアムはほとんど解体してしまいました。大学と地域産業の距離感に危機意識を持ったミラノ工科大学の教員たちは、研究成果を地域に落としていくための新しいセンターを作り、今まであまり交流のなかった中小企業にも足を運んで、改めて向き合おうとしている姿が印象的でした。
トリノ工科大学やヘルシンキ工科大学(現・アアルト大学)でも、同じような話を聞きました。大学と地域との接点は、クローズドな研究開発だけではなく、まちづくり、生涯学習、起業支援など幅広いオープンな面で形成されるべきで、多様な相互作用が生まれる関係形成が大事なのです。未来大でも、教員のリーダーシップで、はこだて国際民俗芸術祭、はこだて国際科学祭、地域史料のデジタルアーカイブ化など、じつにバラエティ豊かな地域連携・社会連携を行っています。
いきなり大学と共同研究ができたり、一緒にベンチャーを作ったりできるのは、EUの統計でも全企業の5%以下というデータがあります。95%以上の企業は、大学の研究にアクセスしたり、大学の研究から事業化したりするには壁があって、その壁を越えるための関係形成や学習の機会づくりが必要なのです。時を同じくして、全国各地の大学でも「共同研究」から「社会連携」といったニュアンスへの名称変更が相次いだので、タイミングの良い判断だったと思います。

センスメイキングの重要性
これまで述べてきたように、私の専門は研究コミュニケーション、技術者倫理、地域イノベーションと多様な領域に渡りますが、大きく見ると「社会科学」ということになります。人文科学というと、歴史、文化、人間を対象にした学問ですが、社会科学は文字通り、社会や組織を対象にした学問です。人文科学と社会科学は、重複しているところもありますが、かなり違う性格を持っていると私は思います。
「センスメイキング」という言葉があります。文字通り、「意味を生成する」ということです。もともとは、社会科学の一分野である経営学において、「組織とは何か」を議論する中で生まれた言葉です。よくよく考えてみれば、組織とか社会というのは、目に見えない存在ですよね。つまり私たち1人1人が、頭の中で「組織」という意味を生成することでしか、組織は存在しない。チーム、仲間、社会も同様です。1人1人はまったく違うことを考えているはずなのに、何か求心力が働いて、共同幻想のようなものが立ち現れる。皆さんが所属している組織や社会は、自分の外にある客観的存在ではなくて、皆さんも作り手の1人なわけです。
社会科学におけるセンスメイキングとは、人間1人1人のセンスの集合体こそが社会であり、社会が逆に個人を縛ったり自由を広げたりする中で、個人の総和を超えた存在になっていくという観点です。学生の皆さんにとっても、自分も関与している目に見えないセンスに敏感になることが、この複雑で不透明で予測し難い社会を生きていく上で、とても重要です。
世界中でIT系、技術系が脚光を浴び、平均給与でも高いところを占めているのですが、実際のところ世界で最も重要な意思決定をしている本当のトップ層の人たちは、社会科学系の素養を持っている人たちだと言われています。だから技術系の人も、社会の意味を読み解く教養とか見識を持って、世の中がどうなっているのかを想像する力が必要です。今この世界はたまたまこういう風になっているけれども、もしかしたら別な世界になっていたかもしれない。「今ここにはない何か」をちゃんと想像しながら次を考えることが、最も大切なセンスメイキングだと思います。
目の前のことだけを解決しようとしたり、単に与えられた知識で技術だけを開発したりするのではなく、それが何に使われるのかとか、それがどういう社会を作り上げていくのかとか、今の自分たちはどういう社会で、それを行おうとしているのか、ということを理解した方が、生きていくのも面白くなるし、納得感が出るし、また活躍の幅も広がると思うのです。ぜひ技術者倫理をはじめ、社会科学系の教養を積極的に学んでほしいと思います。